こんにちは、管理者の川上です。
同業他社の方や、利用者家族等の方にとってテーマになるかなと考えている
ゴール設定について、自論を展開したいと思います。
ほとんどの方が病院と在宅――
同じ“医療”ですが、その目的は少し違います。
病院は 「治すこと」 がゴールになりやすい場所です。
検査値を下げる、合併症を防ぐ、手術が成功する…どれもすべて、医学的な「正解」が明確にあります。
一方で在宅はどうでしょうか。
在宅で生活する利用者さんの多くは、加齢や疾患による
ADLの低下や認知機能の変化が避けられない状況 にあります。
「元気だった昔の状態に戻る」
「歩けるようになる」
「認知症が良くなる」
そういった“治ること”をゴールにできないケースは、訪問看護の現場に山ほどあります。
では、私たち訪問看護における ゴール設定 とは何なのでしょうか。
■ 正解は「本人と家族が思う“幸せな暮らし”」
訪問看護のゴールは、
利用者と家族が望む生活を、できるだけ長く、自分らしく続けられること。
医学的な指標よりも大切なのは、
「その人がどう生きたいのか」 です。
たとえば、
・毎朝、自分でコーヒーを淹れたい
・トイレだけは自分で行きたい
・最期の瞬間まで、家の景色を見ていたい
こうした願いが、その方にとってのゴールになります。
医療者が決めるのではなく、
本人と家族と一緒に対話しながら決めていく。
私たちの役割は、「治す」ではなく
“その人の人生を支える” こと。
これが、訪問看護におけるゴール設定です。
■ 「できることが減っていく」=敗北ではない
訪問の現場では、ADLが低下していく場面に出会うことがあります。
できたことが、できなくなる。
歩けたはずが、車椅子になる。
言葉が出づらくなる。
そのたびに、利用者さんやご家族は “失う悲しみ” に直面します。
そこで私たちは、こう考えます。
減っていくものに目を向けるより、今ある力をどう活かすか。
・トイレまで歩けなくなったら、ベッドサイドで排泄できるよう工夫する
・記憶が薄れていくなら、安心できる環境を整えて不安を減らす
・家族が疲弊しているなら、レスパイトや介護サービスをつなぐ
できなくなることは、決して敗北ではありません。
変化に寄り添いながら、その都度ゴールを更新していく。
それが、訪問看護の姿だと私たちは考えています。
■ 家族のゴールも、同じくらい大切に
在宅は、家族の人生も巻き込んでいきます。
家族にも、守りたい**「生活」**があります。
・夜ぐっすり眠れた
・1時間だけ外出できた
・介護に対して笑顔が戻ってきた
これも立派なゴールです。
訪問看護は看護師だけで成り立っているものではなく、
家族を含めたチーム支援 です。
ゴールが「本人の幸せ」だけに偏ると、
家族が心身ともに疲弊してしまい、結果として在宅生活が立ち行かなくなることもあります。
だからこそ、「家族の負担軽減」も訪問看護の大切なゴールのひとつです。
■ 大切なのは、「いま、この瞬間をどう生きたいか」
訪問看護のゴール設定は、たとえるなら
その人の物語を、一緒に紡いでいく作業。
そして、その物語の主役は医療者ではありません。
主役は、利用者さん。
脇役は、家族。
私たちは、その物語を支える裏方だと、そのように自負してます。


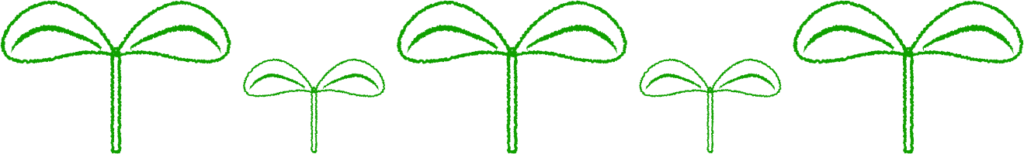

コメントを残す