こんにちは、管理者の川上です。認知症対策にリハビリ含めて力を入れいてる今日この頃です。
突然ですが、脳も“筋肉”と似ていると思いませんか?
動かせば動かすほど活性化し、使わなければ衰えていく。
「認知症予防」において、この視点はとても大切です。
私たち訪問看護は、まさに“脳の筋トレコーチ”として、利用者様の暮らしの中に溶け込みながら、予防や早期発見に関わることができます。
今回は、「認知症予防」と訪問看護の関わり方について、本人、ご家族、そして他の医療・介護関係者とどう向き合うかをお話しします。
■ 本人との向き合い方:小さな変化を“温かく”拾い上げる
認知症予防のカギは、「日常」にあります。
たとえば、「昨日話したことを今日も繰り返す」そんな場面に出会ったとき、ただの物忘れか、初期のサインか。
訪問看護は、定期的に関わるからこそ、変化に気づけます。
ですが重要なのは、“ただ気づくだけ”ではありません。
「昨日のお話、今日も聞かせてくれるってことは、それだけ大切なことだったんですね」と寄り添いながら会話を重ねる。
記憶を責めるのではなく、「その人の世界」を一緒に歩くことが、予防にもつながります。
■ ご家族との向き合い方:見守る力を“焦らず”育てる
ご家族の多くは、「なんとか進行を止めたい」と願っています。
その気持ちは、医療者としても痛いほどわかります。
けれど、認知症予防においては「焦り」が逆効果になることも。
たとえば、「また忘れたの?」という一言が、本人の自己肯定感を奪ってしまうこともあるのです。
私たちは、ご家族にこう伝えます。
「ご本人の“できる”を引き出すサポーターになりましょう」と。
具体的には、一緒に家事をしたり、昔の思い出話を引き出したり、日々のコミュニケーションの中で自然な“脳の刺激”を作るサポートを提案しています。
■ 医療・介護関係者との向き合い方:「情報共有」は最大の予防
認知症は、ある日突然進行するものではありません。
日々の些細な変化が積み重なって、ゆっくりと現れてきます。
だからこそ、訪問看護だけで支えるのではなく、ケアマネジャーさん、主治医、訪問介護、デイサービス…地域のチーム全体で見守ることが重要です。
私たちは、定期的な情報共有の場を大切にし、
「昨日はこんなことがありました」
「最近、表情が柔らかくなっていますよ」
そんな声を積極的に届けることで、予防のための“チーム医療”を実践しています。
■ 最後に:訪問看護だからこそできる“認知症予防”
認知症予防は、「治す」よりも「寄り添う」ことが求められます。
そしてその寄り添いは、病院でも施設でもなく、「暮らし」の中でこそ効果を発揮します。
訪問看護は、その“暮らしの現場”に入り込むことができる、数少ない医療職です。
だからこそ私たちは、単なる看護ではなく、
“その人らしさ”を守る伴走者として、これからも認知症予防に向き合っていきます。


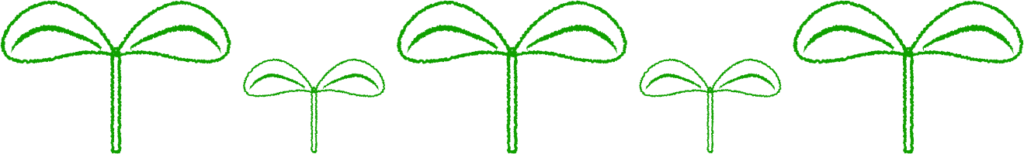

コメントを残す