〜私たち訪問看護ステーションができること〜
こんにちは、管理者の川上です。現場スタッフとともに介入していて、
転倒からの骨折や体調不良による入院等でもよくあるんですが、
在宅に戻ってこられる方の認知機能の低下等が顕著になります。
日常生活の中でも徐々に低下していくことはあります。
日常生活ゆえに、低下が見落とされることも多く、(悩むこともあるかもしれません)
「最近、母が同じことを何度も聞いてくる」
「父が料理の順序を間違えて火を出しそうになった」
「以前より人との会話を避けるようになってきた気がする」
…そんな“小さな気づき”が、実は認知症の初期サインであることもあります。
けれど、「まだそこまで深刻じゃないし…」「病院に連れて行くほどじゃないかな」と、誰にも相談できずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
私たち訪問看護ステーションは、そんな“はじめの一歩”に寄り添い、地域で支える力になりたいと思っています。
1. リハビリスタッフによる、暮らしの中での認知機能アプローチ
「最近、足元がふらついて転びそうになったことがあるんです」
そんな言葉をきっかけに訪問を始めた80代の女性。お話を伺っていくうちに、軽度の認知機能の低下が見えてきました。
リハビリスタッフは、単に運動機能を支えるだけではありません。たとえば…
- 「一緒に買い物リストを書いて、料理をしましょう」
- 「今日は何曜日ですか? 朝ごはんは何を食べましたか?」
- 「昔よく通っていた場所を、地図を見ながら一緒に思い出してみましょう」
こんな風に、会話や作業、運動を通じて“考える機会”を自然に生活の中に取り入れます。これが、初期段階の認知症にとってとても大切なアプローチなのです。
2. 経験豊富なスタッフが“いつもと違う”に気づくこと
私たちの看護師・療法士は、認知症ケアに長年携わってきたスタッフが多く、ちょっとした変化にも敏感です。
あるご利用者様では、
「いつも笑顔で迎えてくれるのに、今日はうつむいて会話も少ない」
「最近、服薬の管理が難しくなっているようだ」
そんな違和感を丁寧に観察し、ご家族と連絡を取り合い、かかりつけ医に状況を報告しました。早めの受診につなげることで、大事に至らずにすんだケースもあります。
日々の訪問は、短時間ではありますが、まるで“生活のパートナー”のように寄り添う存在です。ご本人にも「ここでなら安心して話せる」と思ってもらえるよう、信頼関係を築くことを大切にしています。
3. 地域医療との連携で、「こんなとき、どうすればいいの?」に応える
たとえば、認知症の進行で夜中に徘徊が増え、ご家族が心身ともに限界だったケース。
私たちは訪問診療の先生、ケアマネジャー、地域包括支援センターと連携し、「夜間の対応方法」「服薬の見直し」「短期入所の調整」などを迅速に検討しました。
ご家族からは後日、
「“どうしたらいいか分からない”という不安に、ちゃんと“答え”を出してくれた。ほんとうに救われました」
というお言葉をいただきました。
このように、医療・介護のネットワークを活かし、ご本人とご家族の“困った”にすばやく応える体制を整えています。
最後に:小さな変化を見逃さずに
「まだ大丈夫」と思っていても、ご本人は不安を抱えていたり、ご家族は見えない疲れをためていたりするものです。
私たちは、医療者であると同時に、「人として寄り添う」ことを大切にしています。
大切なご家族の「その人らしい暮らし」を、これからも守っていくために、ぜひ一度、私たちにご相談ください。
また、認知症に関して課題を感じている医療職・介護職の方々との意見交換等もやれるといいなと思っています。ぜひそちらもお問い合わせいただけると幸いです。


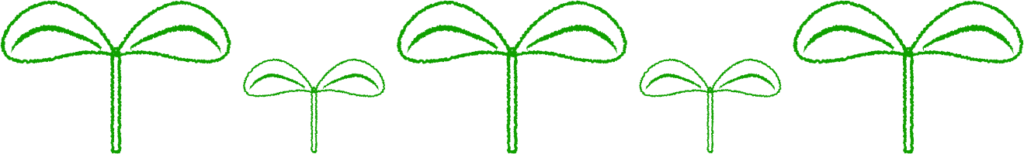

コメントを残す