こんにちは、管理者の川上です。先日認知症について、少し触れました。
多くなってきてるとケアマネさんたちも実感してきている中で、
きっとご家族等はよりそこに対して敏感になってるのかもしれません。
気づくキーワードのようなものがあるのかなと思いますが、
「最近、物忘れが増えてきたかも…」
そんな何気ないひと言に、認知症の“はじまり”が潜んでいるかもしれません。
超高齢社会の今、医療現場で認知症への対応は避けて通れないテーマです。
しかし──
「まだ早い」ではなく、「今こそ」 が、介入のタイミングであることをご存じでしょうか?
◆ 認知症は「予防」できる時代へ
これまで認知症といえば「進行を見守る」ものという印象が強かったかもしれません。
ですが、近年の研究や実践では、以下のアプローチにより予防・進行抑制が可能であることが示されています。
- 早期発見・早期診断
- 薬物療法の適正使用
- 適度な有酸素運動
- 認知機能トレーニング
- 生活習慣の改善(睡眠・栄養・社会参加など)
特に、認知機能がまだ保たれている軽度認知障害(MCI)の段階での介入が、その後の進行を大きく左右します。
◆ 訪問看護が担う「在宅での認知症予防」
訪問看護は、まさにこの**“初期段階での気づきと支援”**を行える立場にあります。
私たちは以下のようなアプローチで、ご本人とご家族をサポートしています。
✅ 認知機能のアセスメント
簡易スクリーニングツールや日常生活の観察から、認知の変化を早期に察知します。
✅ 医療機関へのスムーズな橋渡し
「まだ病院には行きたくない」という心理的ハードルを下げ、ご本人やご家族への受診勧奨を丁寧に行います。
✅ 専門職による運動療法
転倒予防だけでなく、脳血流を促進し認知機能にアプローチする運動を個別に提供します。
✅ 生活習慣の環境調整
起床・就寝・食事・活動のリズムを整える生活支援を通じ、認知機能の安定を図ります。
✅ 認知機能トレーニング
パズルや会話、回想法、タブレットを活用したトレーニングなど、在宅での「脳活」を継続的に支援します。
◆ 医療職の皆様へ:多職種連携で築く「認知症にやさしい地域」
認知症予防・支援は、医療・介護・地域資源が連携してこそ本領を発揮します。
私たち訪問看護は、医師やケアマネジャーの皆様と密に連携しながら、**「在宅での予防と尊厳ある生活の継続」**を支えていきます。
「この人、もしかして…」
そんな直感を、地域全体で受け止められる仕組みを一緒につくりませんか?
ご興味のある医療従事者の皆様へ、具体的な事例の共有や連携体制のご相談も随時お受けしています。
ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。
“気づける”から、“支えられる”へ。
訪問看護がつなぐ、認知症予防のフロントライン。


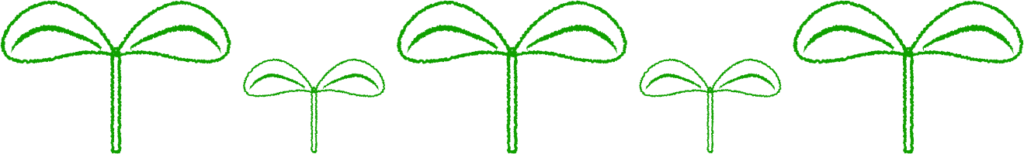

コメントを残す